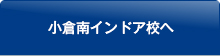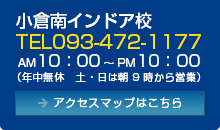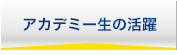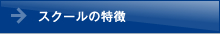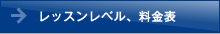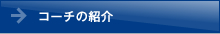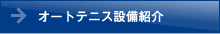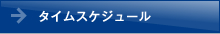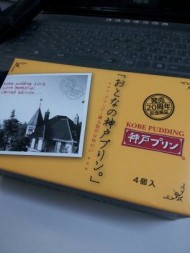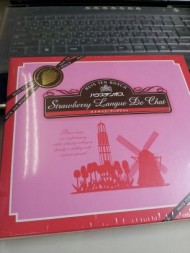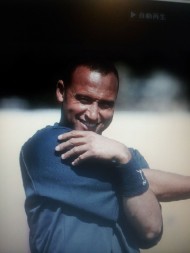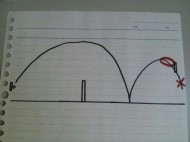ブログ内検索
最近の投稿
- お知らせ 2016年11月11日
- 祝!全日本ジュニアテニス選手権18才以下男子ダブルス優勝 2016年8月17日
- 快挙 2016年8月15日
- 新門司カップ第28回女子シングルストーナメント結果 2016年8月9日
- 新門司カップ第28回女子シングルス結果!!・・・・は後回しで祝!日本一 2016年8月8日
- 祝! 春夏連覇 2016年8月5日
- おねだりブログ バースデイ編 2016年7月29日
- 新門司カップ第30回男子シングルステニストーナメント結果 2016年7月24日
- おねだりブログ 2016年7月24日
- おねだりブログ 2016年7月15日
アーカイブ
- 2016年11月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月